
一方で、何をしているのかわからないという人も多いところと言えます。

結論
覚えるのではなく考えるです。
1.原価計算における製造間接費予定配賦計算とは

原価計算において、製造間接費を予定配賦する場合があります。

価格差異や操業度差異など、理解できると有益と言えます。

2.製造間接費は苦手な人が多い
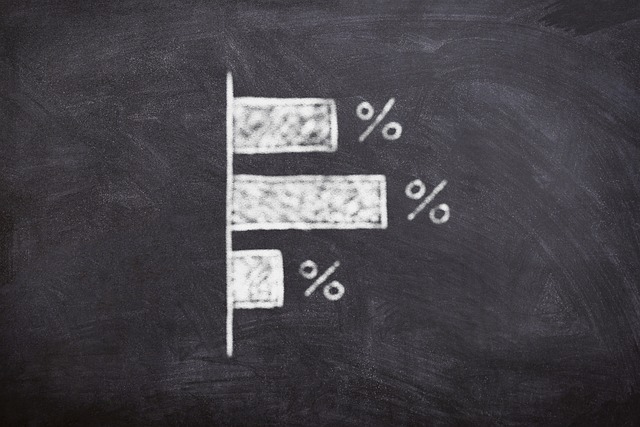

会計処理方法が分かっている人でも、なぜそのように処理しているかは分かりません。
実践的に学んでいくためには、何をしているのか理解する必要があります。
実質重視の学習を行い、暗記の状態をなくす意識が大切です。
3.原価計算における製造間接費予定配賦計算のコツ【3選】

原価計算における製造間接費予定配賦計算のコツ【3選】は、以下の通りです。
3-1.予算の設定

先ずは、予算の設定です

変動予算の種類は、公式法や実査法などです。

製品1個あたり計算できない原価が会計期間でどれぐらいかかるのか、想定していると考えておきましょう。
3-2.時間

次に、時間です
製品1個作るのに、どれぐらいの材料がかかったのか、1人の人が何時間作業にあたっていたのかは明確かもしれません。

つまり、製品1個作るのに0.1時間かかったのであれば、0.1時間分を割り当てるのです。
その際に、手作業であれば直接作業時間、機械作業であれば機械運転時間などを用います。
3-3.部門別

最後に、部門別です
製造間接費は、部門別で予定配賦が基本になっています。

補助部門費の配賦方法について考えていかなければなりません。
補助部門間における取引や、変動費と固定費の配賦に着目していると分かりやすいです。
結論:覚えるのではなく考える
原価計算における製造間接費予定配賦計算のコツ【3選】
・予算の設定
・時間
・部門別
覚えてはいけないわけではなく、覚えた後考える意識をもちましょう。

難しく感じる部分ではありますが、1つずつ理解していけば後が楽になります。
では今回は以上です♪
ご視聴ありがとうございました(^^)/

